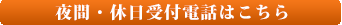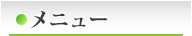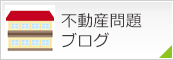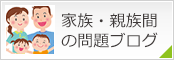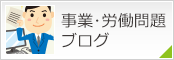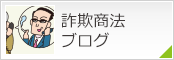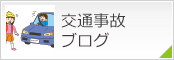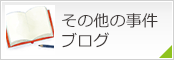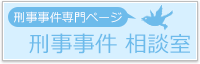風営法違反事件 2
- 2015年03月02日
- その他事件の事例, 事業・労働問題の事例, 刑事事件の事例
◆ 事案の概要
本件の依頼者は、“無店舗型”性風俗特殊営業の届出をした上で、「受付所」を開設し、営業をしていました。
その営業システムは、次のようなものでした。
まず、「受付所」に来所した客に、写真で、好みの女性と受けるサービスのコースを選んでもらい、規定料金を支払ってもらいます。
次に、どこのホテルや施設に女性を派遣するのかを客に尋ね、客が指定する場所に女性を派遣します。
但し、客がホテル等の場所を指定せず、客から「近くにどこかいいホテルはないか?」などと尋ねられたら、「Bホテル」を紹介していました。
ところが、「Bホテル」は、風営法28条2項により、“店舗型”風俗特殊営業が禁止された区域内にありました。
そのため、依頼者は、禁止区域内において“店舗型”性風俗特殊営業を営んだとして、逮捕勾留されてしまいました。
◆ 解決内容
依頼者の弁護人となり、担当検察官に対し、直ちに、「本件事案は風営法28条2項に該当しない」との「上申書」を提出しました。
すなわち、依頼者の経営する「受付所」と「Bホテル」は、経営者を異にし、距離も一定程度離れており、「受付所」を訪れた客を必ず「Bホテル」で接待するというわけでもなかったので、同種事案において、東京高等裁判所の判決が示した「受付所が自店建物内の個室を使用するのと全く同様のものとしてホテルを使用していたと認められる場合」には、該当しないと考えたのです。
「上申書」では、この点を述べるとともに、「万が一にも検察官が本件事案を起訴するのであれば、この点について徹底的に争う」との意向を明らかにしました。
この結果、依頼者は満期まで勾留されたものの、処分保留のまま釈放され、最終的には不起訴処分となりました。
◆ 弁護士のコメント
実際は、起訴されてしまうと、後の裁判の過程で法律論を争うことは、極めて困難です。
逮捕・勾留は、比較的一定の嫌疑があればされてしまうというのが実態なので、本件のように、その嫌疑に疑義がある場合は、弁護人は検察官に対し、逮捕勾留が不当であることを主張し、万一起訴されるようなことになれば、法廷において徹底的に争うのだという姿勢を示すことが大切です。
弁護人が、公判廷において徹底的に争うという姿勢を示した場合、検察官としては、よほどの自信がない限り、起訴することを躊躇する傾向にあります。
検察庁は、99%以上の有罪率(起訴された事件について、有罪になる率)を誇っており、検察官にとって、起訴した事件が無罪になってしまうということは、耐え難い屈辱だからです。
従って、逆に、弁護士が徹底的に争う姿勢を示す場合、必ずしも証拠が十分でないような場合には、不起訴処分とせざるを得ない場合も多くなります。